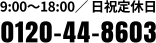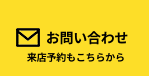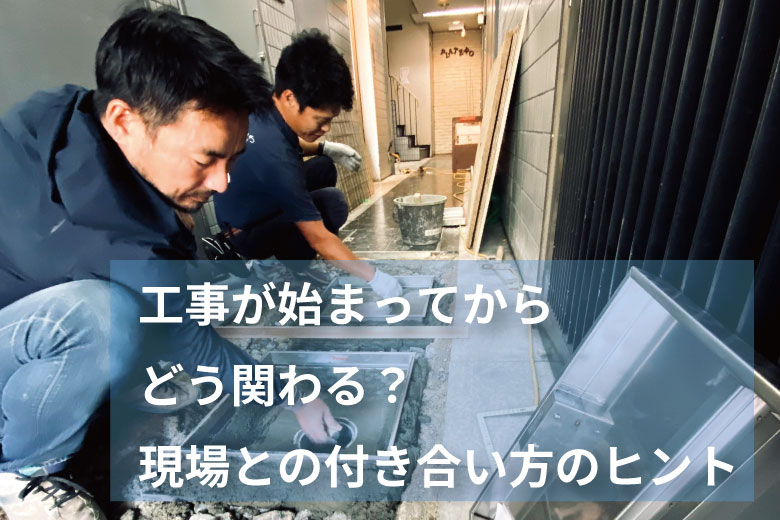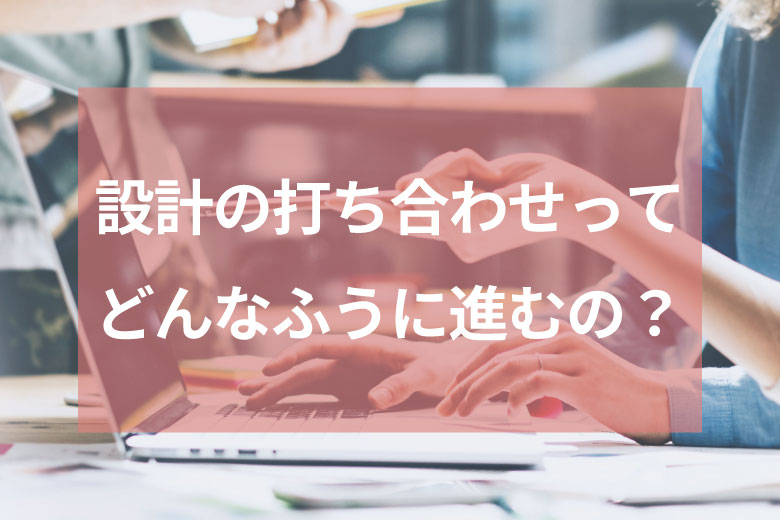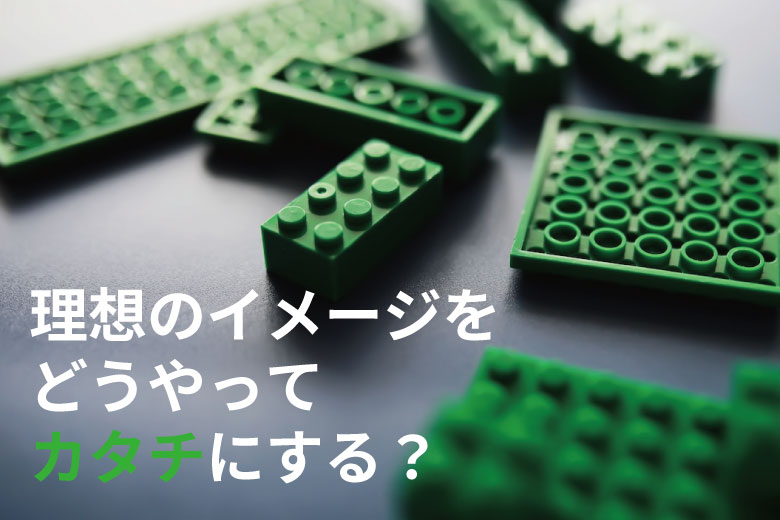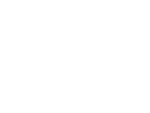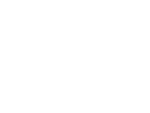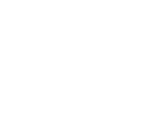- ホーム
- 打ち合わせ
ARCHIVE 2025年06月
-
【京都リノベ】工事が始まってからどう関わる?現場との付き合い方のヒント
現場が動き出してからの時間も、大切なプロセス契約が終わって工事が始まると、いよいよ空間が少しずつ「カタチ」になっていく時期に入ります。図面や打ち合わせで考えてきたことが、現場で立ち上がっていく様子を見るのは、ちょっと感動する瞬間でもあります。とはいえ「現場ってどんなふうに関わればいいんだろう?」と思われる方も多いかもしれません。そこで今回は、工事中の関わり方について少しだけお話してみます。【ポイント】現場とのコミュニケーション、どうすればいい?基本的に現場には担当デザイナーが入り、職人さんとのやりとりを行います。進行状況の報告や、確認したいポイントが出た場合は、デザイナーからタイミングを見てご連絡を差し上げます。気になることがあれば、遠慮なくご相談ください。現場確認に立ち会っていただく機会も随時ご案内しています。実はこの現場確認、デザイナーにとってはちょっと緊張する場面でもあったりします。というのも、現場では職人さんたちの段取りがどんどん進んでいくんですね。「次ここ進めるで、早よ決めてな」なんて言われることも。でもこれ、怒られてるわけではなくて、職人さんとのコミュニケーションの一部なんです。お互いの信頼関係があるからこそ、そんなやりとりが笑いながらできる現場が、リノファクでは当たり前になっています。“見て・感じて・考える”時間を大事に現場が立ち上がってくると、「あれ、もうちょっとこうしたいかも」と感じることが出てくるのが自然なことです。たとえば、 実際の光の入り方を見てクロスの色味を再検討したい 立ち上がった壁のバランスを見て室内窓のサイズを調整したい コンセントの位置を実際の使い勝手を想像しながら微調整したいこうした“現場での気づき”を丁寧に拾い上げていくことが、納得のいく仕上がりにつながります。デザイナーも、正直なところは早く指示を出したいと思ってます。でも、現場で空間が見えてくると「これで本当に良いかな?」と悩むこともある。そんなときはぜひ一緒に悩んでほしいんです。「この壁、もう少し明るい色の方が広く感じられるかな」とか、「この高さでどうかな?」といったやりとり、実は職人さんにも聞いてみてください。「職人さんだったらどうしますか?」と聞くと、意外なほど真剣に考えてくださる方ばかりで、そこからより良いアイデアが生まれることもあります。僕たちデザイナーも、現場では職人さんにいろいろ聞きます。「これ、もうちょっと納まりきれいにできる?」なんて相談もよくするし、そんなやりとりができる現場って、やっぱりいいなと思っています。【大切にしていること】現場の空気感づくりリノファクの現場は、お客様から「職人さんもデザイナーさんもすごく話しやすかった」と言っていただけることが多いです。これは、私たちが「現場もチームの一部」として、一緒につくる仲間として関わっているからかもしれません。職人さんも「こうした方がもっと良くなるかも」と提案してくれたり、細かいところまで丁寧に仕上げようという空気が自然と現場に流れています。そんな雰囲気の中で工事が進むと、お客様も現場に顔を出しやすくなり、気になることを言いやすくなる。それがまた、より良い住まいづくりにつながっていくと考えています。まとめ:現場は“つくる楽しさ”を味わう時間工事中は「決めること」「考えること」がまだまだ続きますが、その一方で「つくっていく過程を楽しめる時間」でもあります。壁が立つ、床が貼られる、塗装が入る——その一つひとつを見届けながら、自分の住まいができあがっていく過程を味わっていただけたらうれしいです。私たちも、その時間がいい思い出になるように、丁寧に現場を整えてお迎えしていきます。一緒に悩んで、一緒につくっていきましょう。
-
はじめての打ち合わせ、ちょっと緊張するかもしれませんがリノベーションの設計打ち合わせって、「何をどこまで話せばいいのか」「どんな準備が必要なのか」よく分からないまま始まることが多いです。今回は、実際にどういった流れで進んでいくのか、どんなことを話していくのかを、できるだけ実感を持ってもらえるようにお伝えしたいと思います。打ち合わせの流れ ヒアリング(理想の暮らしのイメージを伺う) 現地調査(建物の状態を把握) ラフプランと概算見積りのご提案 仕様・素材の検討(ショールーム同行やサンプル確認など) 最終プランと工事費の調整・確認 ご契約へ【ポイント】リノファクの打ち合わせが少しユニークな理由リノファクでは、「設計担当」と「施工担当」が別々ではなく、ひとりの担当デザイナーが最初のヒアリングから現場管理まで責任を持って進めるという体制をとっています。これは図面を描くだけでなく、現場で大工さんや塗装屋さん、左官屋さんたちとやりとりしながら、お客様と決めたデザインを実際の空間へと形にしていくための大切な仕組みです。たとえば、「グレーの壁で」とお伝えいただいたときに、設計と施工が分かれていると「標準のグレーですね」と工事が進んでしまうことがあります。でも実際には、ほんの少し青みがかったグレーの雰囲気が理想だった、というようなすれ違いは少なくありません。その点、リノファクではデザイナーが現場に立ち会いながら、職人さんと直接「このトーンに近づけていきましょう」と相談を重ねていくため、完成後の「思ってたのと違う」をできるだけ防げる体制になっています。ご契約までに“整えておきたい”こと打ち合わせの流れの中では、「ご契約へ」というステップがありますが、実はこのタイミングで整っていてほしいのは以下の3つです: 工事図面をもとにした具体的なレイアウト そのレイアウトをベースにした、基本となる仕様の構成 それに対する費用感(見積書)この3つが揃うことで、後からの変更にも落ち着いて対応することができます。特に仕様が変わると、費用が変動するだけでなく、工期にも影響を及ぼすことがあります。よくあるのは、「思っていたより少し違った」と感じて修正を繰り返してしまうケースです。一見、直してもらえているから問題ないように感じるかもしれませんが、実際には大工さんの工事費や処分費などが余分に発生しています。そうなると、工事を請け負う職人さん側にも負担がかかり、現場の雰囲気がギクシャクしてしまうこともあります。お互いにとって、事前にしっかりと合意した内容をもとに進めていけることが、気持ちよく、そして良い現場づくりにつながると私たちは考えています。実際にリノファクの現場では「本当にいい職人さんばかりですね」といった声をいただくことも多く、「こうしたらもっとよくなるんじゃない?」と職人さん側からも提案が出るような、和やかで風通しのいい現場が特徴です。工事が始まってから“わかってくること”もあるリノベーションは、契約して終わりではありません。むしろそこからが設計の実践のスタート。描いていた図面やイメージが少しずつ現場に立ち上がってくる中で、確認を重ねながら丁寧につくり上げていきます。たとえば、壁が立ち上がったときに「やっぱり圧迫感があるな」と感じて、そこに室内窓を設けて抜け感をつくったり、色のトーンを少し調整したくなることもあります。実際に空間が立ち上がってからでないと分からないことは、たくさんあるんです。そのため、リノファクでは工事が始まってからも「壁の位置や素材感を一緒に確認する」「その場で選びながら、必要に応じて再調整する」というプロセスを大切にしています。【ポイント】“設計の基準”を持つことの大切さ契約時点で図面・仕様・見積書という“設計の基準”があることで、そこから増やす・削る・調整するという判断がしやすくなります。この基準が曖昧なまま工事が始まってしまうと、結果的に「思っていたのと違う」というズレが起こりやすく、余分な修正や追加費用がかかってしまうケースもあります。何度も修正を繰り返すと、現場の職人さんにも負担がかかりますし、丁寧な施工をお願いしづらくなってしまう可能性もあります。だからこそ、お互いが安心して気持ちよく工事に向き合えるように、事前の準備と合意がとても大切だと考えています。設計打ち合わせは、一緒に「暮らしを編集する」時間図面を描くことが目的ではなく、「どう暮らしたいか」を一緒に考え、整理し、カタチにしていく過程そのものが設計打ち合わせです。「朝の支度をもっとスムーズにしたい」「子どもが帰ってきたときに顔が見えるリビングにしたい」など、言葉にしにくい願いや小さな違和感を、一緒に拾い上げていけるような打ち合わせを目指しています。うまく言葉にできなくても大丈夫です。スタッフと一緒に“編集”していくような感覚で、気になること・悩んでいること、なんでも話してもらえたらうれしいです。
-
「こんなふうに暮らしたい」をうまく伝えるために リノベーションを考え始めたとき、まず浮かんでくるのは「どんな家にしたいか」という理想のイメージ。ただ、このイメージを誰かに伝えるって、思った以上に難しいなと感じる方も多いかもしれません。実際、私たちがご相談を受ける現場でも、参考写真や切り抜きをベースにお話しいただくことがとても多いです。それ自体はすごくありがたいことなんですが、そこで一つ気をつけておきたいのが、「その写真のどこに惹かれたのか?」という視点です。たとえば、カウンター越しの壁の色合いが気になったのか、カウンターに座っている雰囲気に惹かれたのか。同じ写真でも、人によって見ているポイントや感じ方って全然違います。その理由を少し立ち止まって考えてみる。これは、私たちデザイナー側も意識して丁寧にお伺いするところですが、施主さん自身にも「なんでこれ選んだんやろ?」と一度問いかけてみてもらえると、イメージがより深く整理されていきます。1.近づいたり離れたりしながら考えてみるリノベの初期段階では、どうしても目の前の気になる写真や素材に目が向きがちです。でも、そこにぐっと近づきすぎると、大きな方向性が見えにくくなることもあります。たとえば「このタイルが可愛い」「この取っ手が好き」といった具体から入るのもいいんですが、先に全体像が描けていないと、細部だけ整えてもどこかちぐはぐな仕上がりになることも。なので、まずは少し引いた目線で「どんな生活がしたいか」というところからスタートするのが、結果的に納得のいく空間づくりにつながっていきます。2.暮らしの雰囲気を描いてみるわかりやすいところでいえば、「大きなリビングが欲しい」「寝室は個別がいい」「子どもは何人くらいで考えている」など、暮らしの規模感や関係性をイメージするところから。「帰ってきたときにリビングを通って子どもと顔を合わせたい」「個室よりも開放的なワンルームに近い形がいい」など、日常の動きや価値観も含めて、「こう暮らしたい」が少しずつ形になっていきます。この“生活の雰囲気”を一緒に考えることが、私たちが何より大切にしているステップのひとつです。3.好きなものを集めることも、やっぱり大事とはいえ、具体的な写真やテクスチャーを集めておくことも、やっぱり大切です。まずは気になるものを、ジャンルを問わずどんどん保存してみてください。その中から「共通点」が見えてくることもありますし、最初は自分でも言葉にできなかった“好き”が、だんだん形になってくることもあります。写真一枚からでも、そこに込められている感覚やイメージを丁寧に引き出していく。そんな対話を通して、住まいの全体像を一緒に膨らませていくのが、私たちの役割だと思っています。まとめ:イメージは、対話の中で育っていく理想のイメージって、最初からはっきりしていなくて当然です。むしろ、「なんかいいな」っていう曖昧な感覚を、デザイナーと一緒に少しずつ形にしていくことが、リノベーションの面白さでもあると思います。だから、うまく言えなくても大丈夫。好きなものや、気になる写真、ふと思い浮かんだ暮らしの場面。そういった断片をきっかけに、ぜひ一緒に考えていけたらうれしいです。